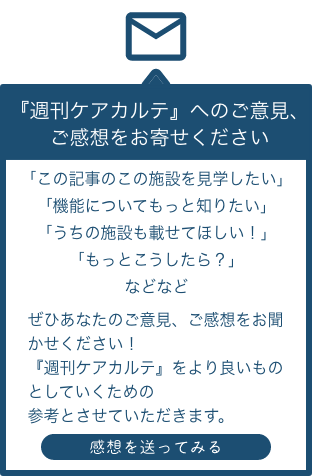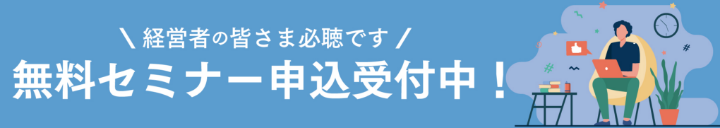2つあったシステムを1つに集約
ー ちょうじゅ(ケアカルテ)導入のきっかけは何ですか?
もともとは手書きで記録を管理していましたが、岡山のシステム会社に独自の記録システムを作ってもらって、サーバーを入れてパソコンで記録の管理をするようになりました。
スケジュール管理やケアプランはエクセルで作成して、請求は別のシステムを使っていましたね。
2つのシステムを使っていたので、転記の多さによる無駄な業務を削減したいと思ったのと、独自の記録システムが使いづらく統一した様式でのデータ管理と情報共有をしたかったので「システムを一斉に変えたい!」と考えるようになりました。
システムを変えることでこだわった点は、クラウドを使うということ。
クラウドで使えるのならタブレット端末を利用して記録時間の削減もできるし、どこでも記録が見られるということで、ちょうじゅ(ケアカルテ)を選びました。
最初、他システムとちょうじゅ(ケアカルテ)が選定対象となっていましたが、近隣施設の庄の里さん(社会福祉法人和福祉会 庄の里さま)がちょうじゅ(ケアカルテ)の導入を始めたと聞いたので、セレーノ総社でもちょうじゅ(ケアカルテ)を導入しようと決めました。

ー ちょうじゅ(ケアカルテ)導入当初はカスタマイズツールを駆使していたと聞きました。
いくつかの書類はちょうじゅ(ケアカルテ)の中に取り込みましたね。介護保険証とか生年月日とか、すでに入力されているものは他の帳票にも引っ張ってこれることを現場の職員も分かっていて、入れられるもの(帳票など)はどんどんちょうじゅ(ケアカルテ)に入れましたね。
(※現在はカスタマイズツールの提供は終了しています)
簡単にできる検索機能が便利
手書きの方が早いと思う職員もいるかもしれないけれど、ケアカルテに入力した記録は簡単に検索にかけられたり、特定の情報だけ抜き出して記録を作り直したりできるので便利だと思います。
最初に居宅を利用していた人がデイを利用して、最終的に特養を利用したとしても、最初からの記録を追えるので法人内での記録の情報共有もできますしね。

使い続けることで、無くてはならないものに
ー ケアカルテを利用されている職員の方の評価はいかがですか?
ちょうじゅ(ケアカルテ)を導入し始めた頃は、旧システムからの引き継ぎや記録ルール作成、職員への周知に苦労して「手書きの方が楽だ」「記録の入力がしづらい」などの反対意見も多かったです。でも、スマホの普及もあり比較的スムーズに導入できたのではないかとも感じています。導入後は、現場発信で書類削減の意欲も出てきて、手書きの記録はかなり削減できています。
また、外国人職員も定型文の入力やタブレットでの記録入力がしっかりとできています。
導入してから6年も経っているし、ケアカルテがないと仕事が進まないので今はもう反対意見は特にないですね。

ー ケアカルテに追加してほしい機能などはありますか?
ケアカルテは記録の入力チェックはまだできないですよね。
「ここの記録入っていない!」「いない人に記録が入っている!」などのチェック機能がほしいですね。真面目なスタッフが多いから、記入漏れがないかひとつひとつ確認していて、間違いを自分たちでなおしているんです。
AIなどの機能でチェックできるといいですね!

シルバーセンターセレーノ総社
システム導入をはじめ、つねに新しいことを取り入れている雪舟福祉会さまでは、BCP策定としての『LINE WORKS』の活用や地域交流を目的としたカフェの開催、他法人と協働し地域の福祉ニーズに幅広く対応する『ふくしネットそうじゃ』での活動など、さまざまな取り組みを行なっています。
今後も雪舟福祉会さまの取り組みをご紹介していく予定です。お楽しみに!

地域食堂のみなさん